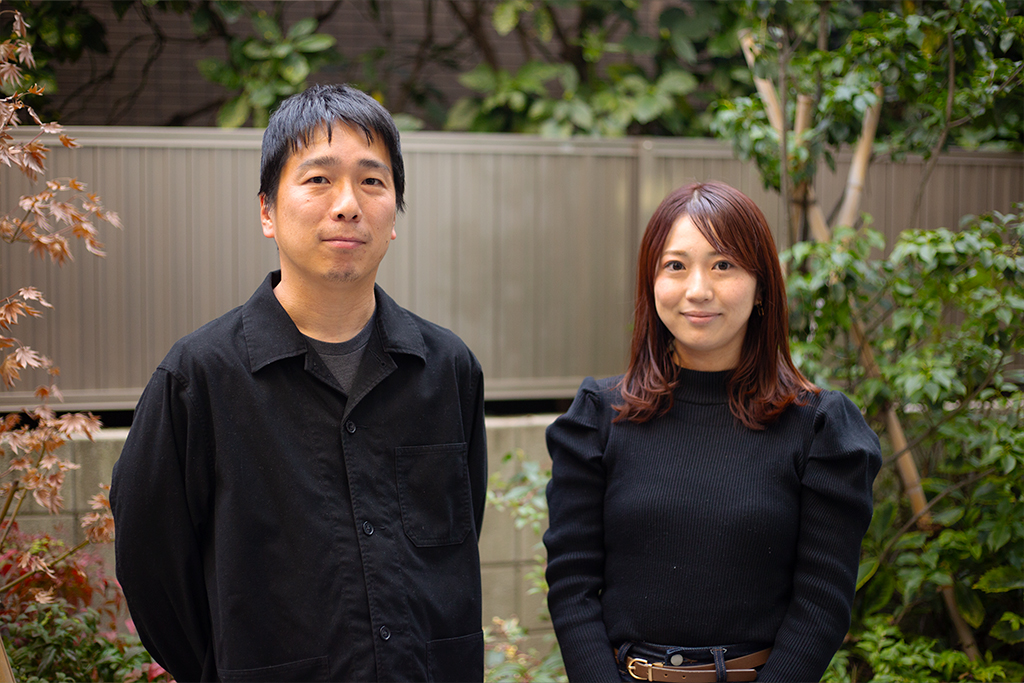正社員エンジニアがゼロの体制から、技術組織の立ち上げへ。採用活動の立ち上げ期にLAPRASを導入し、約1ヶ月半でCTO候補との出会いを果たしたのが、採用支援プロダクト「RekMA(リクマ)」を手がけるHaulです。技術そのもの以上に、“その人らしさ”を見つけ、丁寧に届ける。候補者の温度感を掬い取り、双方向のコミュニケーションで信頼を築く。LAPRAS × RekMA──ふたつのプロダクトが連携することで、Haulが目指した「選ばれる採用」のあり方とは。人事の福田さん、そしてCTO候補として入社した北畑さんにお話を伺いました。
《プロフィール》
HR
福田 奈央さん(写真右):
メガベンチャーに新卒で入社後、営業・広報・人事など幅広い職種を経験。育休復帰を機に環境を変え、2023年にHaulへ1人目社員として入社。現在は人事を軸に、労務・秘書などバックオフィス全般を担う。会社の成長フェーズに合わせて採用体制を整え、カルチャーの基盤づくりにも注力。子育てと仕事を両立しながら、Haulの挑戦を支えている。
フルサイクルエンジニア
北畑 建さん(写真左):
SIerからキャリアをスタートし、複数のベンチャーで開発責任者やCTOを歴任。プロダクト開発から組織づくり、採用まで広く携わってきた中で、「もう一度、現場で本気のものづくりがしたい」と強く感じるようになる。40歳を前に再びスタートアップの渦中に身を置くことを決意し、2024年Haulへジョイン。人や想いが自然と集まってくるHaulの可能性に惹かれ、1人目エンジニアとしてプロダクト開発と組織の土台づくりに挑んでいる。
株式会社Haul:
「希望ある未来を実装する」をビジョンに掲げ、採用領域の課題に向き合うスタートアップである。2018年の創業以来、テクノロジーと実践知を掛け合わせ、企業の採用活動を支援するプロダクトやサービスを展開。採用支援SaaSの開発・運用に加え、伴走型の採用パートナー事業や、エンジニア向けの技術スタックデータベース「what we use」の提供など、多角的な取り組みを通じて、採用の現場に変化を生み出している。
RekMA(リクマ):
“採用の成果創出”に着目した次世代型の採用ソリューション。候補者毎にパーソナライズされた最適アプローチにより、本当に欲しい人材の採用をサポートしている。
従来の企業が選ぶ「見極める採用」から、候補者に選ばれる「アトラクト採用」へ。企業の採用活動を仕組みごとアップデートしていくプロダクトである。
<サービスリニューアルのお知らせ>
法人向け採用サービス「LAPRAS」(旧:LAPRAS SCOUT)が新しくなりました!◆採用課題に合わせた3つのプランをご用意
運用代行、自社運用、成功報酬特化型などバリエーション豊富!
・ミドル~シニアエンジニア採用に強い高品質DB
・コスト削減、工数削減など多様な採用ニーズに対応!
・プランごとの違いがひと目でわかる比較表アリ
※記事中に「LAPRAS SCOUT」の文言がある場合は「LAPRAS」と読み替えてください。
目次
LAPRASなら職歴以上にリアルな候補者が見える
― はじめに、LAPRAS導入に至った背景から伺ってもよろしいでしょうか?
福田:私が入社したのは2023年6月で、当時は正社員エンジニアはまだ在籍しておらず、業務委託の方々と開発を進めている状態でした。目の前のタスクをこなすだけでなく、長期的にプロダクトを育てていくには、戦略をともに描けるエンジニア組織のリーダーとなる存在が必要だと感じていました。
― CTO候補のようなハイレイヤー人材の採用に切り替えたのは、その流れの中で?
福田:はい。最初はメンバークラスでの採用を想定していたのですが、「その先に自走できるチームを築けるか?」と考えたとき、まずは土台を築ける人に来てもらう必要があると判断しました。そこでテックリード〜CTO経験をお持ちの方にターゲットをシフトしました。
― LAPRASを導入したのはいつ頃でしょうか?
福田:LAPRASを導入したのは2024年5月末です。当初は他の媒体や紹介会社も使っていたのですが、なかなか「この人だ」と思える方に出会えませんでした。そんな中、エンジニア採用を支援してくださっていた外部のCTOの方から「Haulの採用にはLAPRASが合うかもしれない」と勧められたのが導入のきっかけでした。
― 実際に触れてみてどう感じましたか?
福田:一番印象に残っているのは、アウトプットベースで“今のその人”が見えることですね。GitHubやQiita、Xの発信と紐づいていて、プロフィールを更新していなくても技術への関心や姿勢が伝わってくる。「この人は現役で技術に向き合っているな」とすぐにわかるUI設計も秀逸だと感じました。
北畑:僕自身もLAPRASに登録してはいたんですが、プロフィールを細かく設定したりはしていません。それでも、自分自身が取り組んできた開発や発信してきた内容を拾ってもらえて、「ちゃんと見てもらえてる」という感覚がありました。
福田:LAPRASは、職歴や肩書では出会えなかった方と出会える場所だと感じましたね。
焦らず、こだわり、組織の土台を一緒に作れるエンジニアとの出会い
― LAPRASではスカウトが要になりますが、どのような運用をされていたのでしょうか?
福田:まずは私が候補者をピックアップし、エンジニア採用を支援してくださっていた外部CTOの方にも目を通していただいて、スカウト文を1通ずつ丁寧にカスタマイズして送っていました。会社概要等は一部テンプレートは使用していましたが、なぜその人にスカウトを送るのかというのはその方に合わせて、GitHubや技術ブログ、スライド資料などを読み込みながら、「なぜこの人に会いたいのか」を言葉にして伝えることを徹底していました。
― 北畑さんへのスカウトも、そのように?
福田:はい。北畑さんには2024年7月上旬にスカウトをお送りしました。SNSなどに情報は少なかったのですが、わずかに見つけたスライドや過去の発言を丁寧に読み込んで、「組織づくりに真剣に向き合ってこられた方だ」と感じたんです。ハードスキルだけではなく、思想や姿勢への共感を中心にお伝えしました。
北畑:あれは印象的でした。私自身の経験に言及されているパーソナライズされた内容で、自分のことをきちんと見てくれていると感じられました。「この会社と一度話してみたいな」と思えるきっかけになりました。
― カジュアル面談はどのように設定されましたか?
福田:スカウト送付後、すぐにやり取りが進んで、2024年7月中旬にはカジュアル面談が実現しました。初回面談には代表の平田が出て、熱量をもって直接お話する形をとりました。初回面談で代表が出るという形で、採用への本気度が伝わるよう意識していました。
北畑:カジュアル面談前に代表の思いがわかる記事を送ってもらっていたのも良かったですね。Haulの事業に対する思いも、すごく伝わってきました。
福田:はい。採用における“本気度”は、相手にも自然と伝わるものだと思っています。だからこそ、「この人に会いたい」と思ったら、会社のトップが動く。面談に誰が出るかという体制そのものが、強いメッセージになると思っています。現在は北畑さんも入社してくれているので、初回面談は北畑さんに実施いただいているケースもあります。
北畑:実際、面談の段階で「この会社は本当に自分を迎えたいと思ってくれている」と感じられました。形式的な面談ではなく、対話としてきちんと向き合ってくれている実感がありました。
選考体験そのものが、プロダクトの第一印象になる
― カジュアル面談の後、選考はどのように進んでいったのでしょうか?
福田:最初の面談で良い感触があったので、その後は代表や他のメンバーたちとの複数回の面談を通じて、相互理解を深めていきました。ここで活躍したのが、弊社プロダクトのRekMAでした。
― 具体的には、どのようにRekMAを活用したのでしょう?
福田:面談後に候補者の方へアンケートを送り、選考の感触や迷い、不安に感じている点などを伺うようにしています。これにより、候補者の“温度感”を可視化し、次の面談にどうつなげるかを考える材料にしていました。
北畑:実際に私も選考の途中でRekMAのアンケートに答えたんですが、あれは本当に印象的でしたね。アンケートを回答することで次回面談で、懸念であげた部分をちゃんと払拭してくれるコミュニケーションをとってくれるので「この会社は、自分の気持ちをちゃんと知ろうとしてくれているし、すり合わせをしっかりしてくれるんだ」という姿勢が伝わってきました。選考の中でこういう気遣いがあると、安心して本音を出せるようになるんです。
福田:アンケートの回答は面接官全員に共有しています。候補者がどこで迷っているか、何を気にしているかを踏まえて、次の面談ではその疑問をちゃんと解消できるよう準備します。たとえば「前回こういう懸念があったと伺っているのですが…」というように対話を設計していくイメージです。
― 面談の質そのものも高まりますね。
福田:はい。そして、RekMAを通じて得られた情報を元に、次回面談や面接の質の向上に繋げことができるよう意識しています。。誠実な対話を重ねることで、ご縁が合った方はもちろん、最終的にご縁がなかったとしても、「Haulは丁寧に向き合ってくれた会社」として記憶に残っていただけたらと思っています。
北畑:私自身、RekMAが選考プロセスに組み込まれていたことで、入社後に携わるプロダクトへの理解が一気に深まりました。「この設問ってどう感じるだろう?」「こういう体験になるのか」と、まさにユーザーとしてプロダクトに向き合う時間でした。
― 候補者でありながら、ユーザーとしてプロダクトを体感されたんですね。
北畑:そうですね。RekMAって、ある意味“コミュニケーションの設計図”みたいな役割があると思っています。ただ情報を得るだけでなく、候補者との信頼を築くための問いや流れがしっかりある。その設計に触れたことで、「もっとこうしたら良さそう」「自分ならこう改善したい」といった発見も自然と生まれました。
福田:RekMAは、導入企業の担当者の声はもちろんですが、選考を受けていただいている候補者からの声もしっかり取り入れて随時プロダクトをアップデートしています。実際に当時選考中であった北畑さんからも、「この設問は選考のフェーズによって変えてもいいかもしれませんね」といったフィードバックをいただき、それがそのまま製品改善に活かされたこともありました。
北畑:選考を受けながら、自分が関わるプロダクトを“体験者”として捉える──これはすごく貴重な経験でした。入社を決めるうえでも、自分の関わる仕事に対して具体的なイメージが持てたのは大きかったと思います。
― 採用プロセス全体を通じて、候補者との関係構築をとても大切にされている印象を受けました。
福田:はい。最終的にご一緒できるかどうかだけでなく、「この会社と出会えてよかった」と思ってもらえる体験をつくることが、私たちにとってはすごく重要です。採用活動そのものを通じてファンになっていただけるような、“出会い方の質”にこだわっています。
― 具体的に、そうした体験づくりで工夫されていることはありますか?
福田:面談やフィードバックの設計はもちろんですが、選考とは別にフランクに交流できる場をつくるようにもしています。たとえば、これまでに「Beer Night (ビアナイト)」と称して、興味を持ってくださった方を少人数でお招きし、カジュアルに話す会を開催しました。
北畑:いわゆる「会社説明会」ではなく、お互いの人となりや価値観を共有できる場ですね。現場メンバーも参加して、最近の開発の話や、どんなふうに働いているかなどをざっくばらんに話しています。
福田:実際に参加いただいた方からは「雰囲気が伝わってよかった」「正式な選考前に話せて安心した」といった声もいただいていて、やってよかったなと感じています。参加後に選考につながった方もいましたし、すぐに応募に至らなかったとしても、「Haulっていい会社だったな」と印象に残ってくれるだけでも意味があると考えています。
北畑:エンジニアにとっては、技術スタックや働き方以上に、「どんな人と一緒にやるのか」が決め手になることも多いですからね。そうした空気感を事前に感じてもらえる場として、こうした交流の機会はすごく有効だと思っています。
「今」を映すアウトプットから、新たな仲間との出会いを
― LAPRASのUIや仕組みについてはどう感じましたか?
北畑:プロフィールや職歴を頻繁に更新するタイプではなかったので、LAPRASのようにGitHubやXなどから自動で情報を収集してくれるのは本当にありがたかったです。自分であれこれ書かなくても、技術的な関心や最近の動きが反映される仕組みは、とても合理的だと感じました。
福田:その意味でも、LAPRASは「今のその人」を見つけるためのプラットフォームだと感じます。転職意欲が明確にある方だけでなく、まだ検討段階にいる方とも出会えるのが、他の媒体との違いだと思います。
北畑:そうですね。私自身、転職を強く意識していたわけではなかったですし、むしろ「なんとなく」見ていただけでした。でも、LAPRAS経由で本気のメッセージが届いたことで、「この人たちと話してみたいな」と思えた。あれがなかったら、Haulとは出会えていなかったと思います。
― まさに“届ける採用”だったわけですね。
北畑:はい。知名度や規模じゃなくて、「言葉」や「想い」で引き寄せられた感覚がありました。逆に言うと、そういうアプローチがなければ埋もれていたかもしれません。LAPRASが自分の情報を集約して伝えてくれていることに価値を感じています。
福田:スカウトの反応率も、LAPRASはとても良かったです。もちろん時間をかけて丁寧に書いているという前提はありますが、「読みたい」「返したい」と思ってもらえる文面に仕上げられるのは、LAPRASの情報の見やすさがあってこそ。技術領域ごとの強みや関心が整理されていて、人物像が掴みやすいUIは、私たちにとっても欠かせない要素でした。
― 今後、LAPRASをどのように活用していきたいですか?
福田:今後も、単に“人を集める”ためではなく、“ともにものづくりをしてくれる仲間と出会う”ために活用していきたいです。LAPRASは、その人のアウトプットを起点に興味やスタンスを捉えることができるので、カルチャーの相性や将来のパートナーとしての可能性も想像しやすい。これからも「届ける採用」の軸として、大切にしていきたいと思います。
北畑:エンジニアにとっても、無理に自分を飾らなくても「しっかりと見てくれる人がいる」と思える仕組みはすごくありがたいです。LAPRASには、自分を探してくれる誰かがいる。それだけで安心感があるし、未来につながる出会いになるんだと感じました。
― 今後のエンジニア採用について、どのような展望を描いていますか?
福田:これからは、中長期的に事業に関わってくれる方との出会いを大事にしていきたいと考えています。特に正社員比率を高めていきたいですね。
北畑:今は正社員エンジニアが私ひとりという状態なので、これから一緒にチームをつくっていける方に出会っていけたらと思っています。これから少しずつ組織を形にしていく段階なので、目の前の開発だけでなく、チームとしてどう動くかを一緒に考えてくれる仲間と出会いたいですね。
福田:直近では、Tech Leadとして技術的にリードいただけるポジションの採用を進めています。あわせて、事業理解にも関心を持って開発できるプロダクトエンジニアのような方を複数名、今年中にお迎えしたいと思っています。
その上で、今回の北畑さんのときと同じように、一人ひとりの方をしっかり見て、納得感のある形で採用していく姿勢は変わりません。スピードを求めすぎず、最適なマッチングを時間をかけて実現していきたいと考えています。
― なるほど!本日はありがとうございました。
※HaulとLAPRASの取り組みに関する公式発表はこちら
「LAPRAS」でハイスキルなITエンジニアをリーズナブルに採用!
- 経験豊富なミドル~シニアエンジニア獲得に強み
- 反応率の良い転職検討層が多数登録
- 多彩なプランで採用コスト・工数削減を実現
経験・スキル・志向性など多角的な候補者情報が一点に集約された効率的データベースです。
優秀なエンジニアを採用するなら LAPRASをぜひご検討ください。
⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら