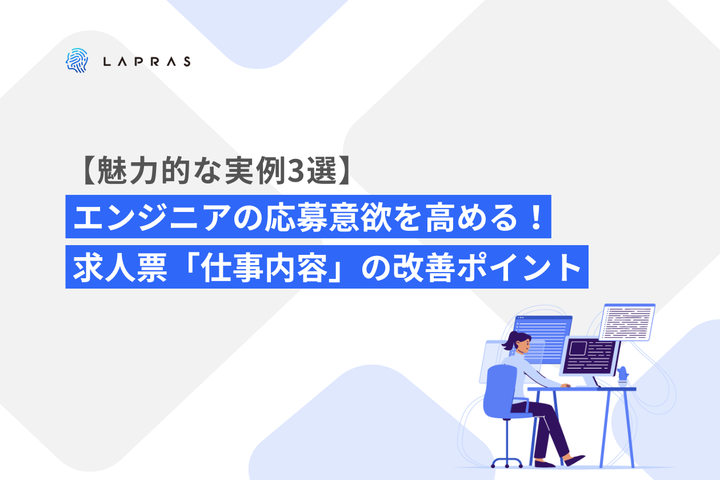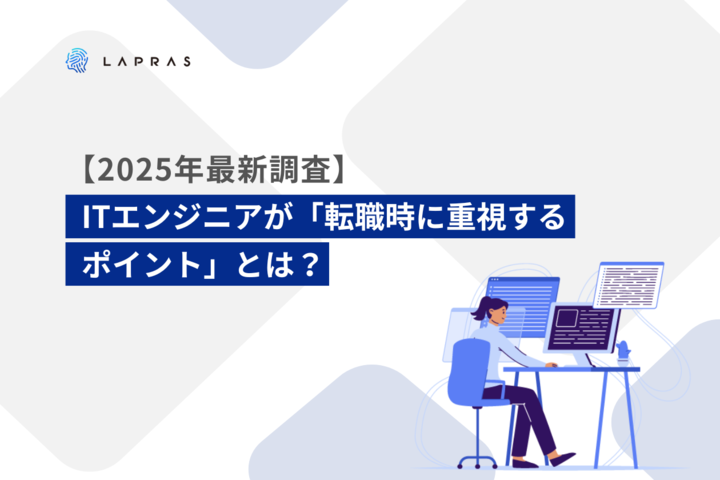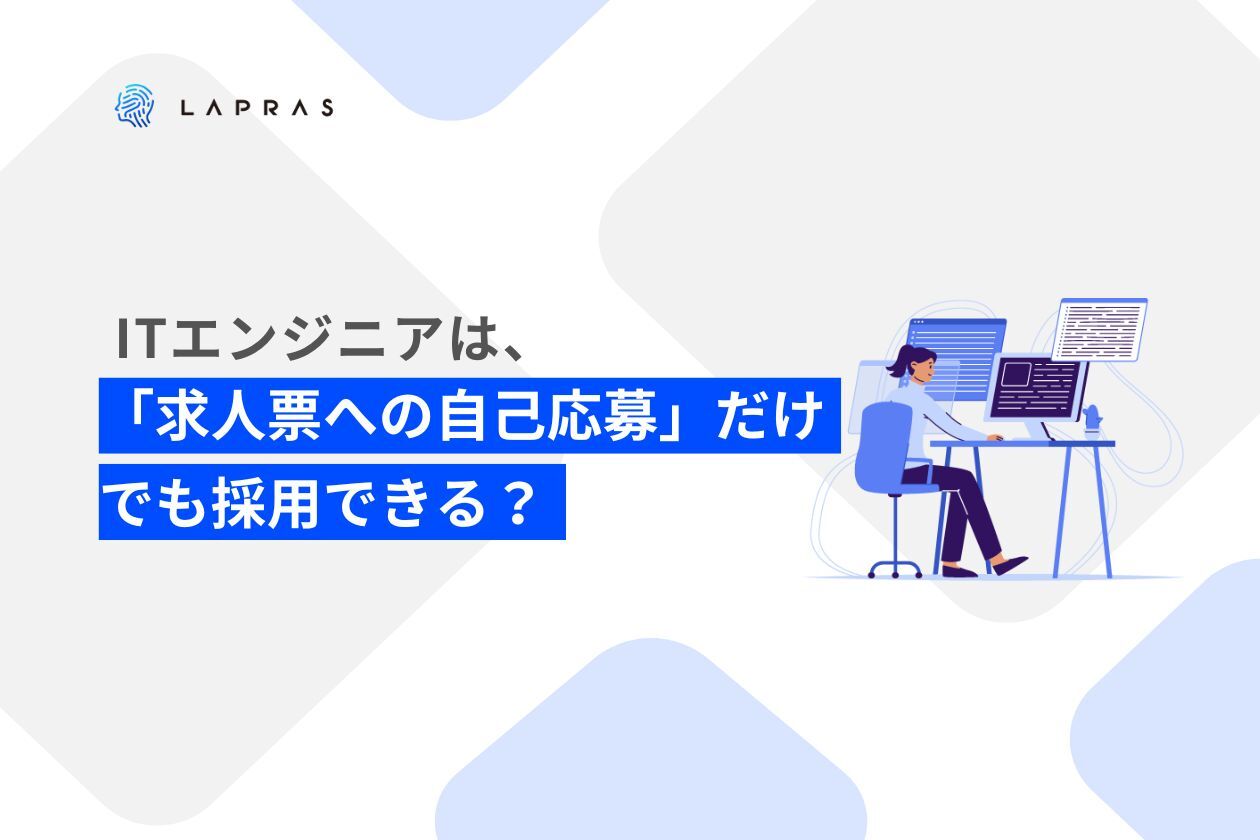この記事は、LAPRASが選んだ「魅力的な求人票」を参考にしながら、候補者の心を掴むために注意するべきポイントを解説するシリーズです。
今回は、求人票の中でも「仕事内容」について説明するセクションを取り上げます。ここでITエンジニアの方々が知りたいのは、「入社後、自身が活躍する姿をリアルに想像できる情報」です。
単なるタスクの羅列に留まらず「どのような技術的課題に、どの程度の裁量を持って取り組めるのか」「入社後、具体的に何から始めるのか」といった、働く姿の解像度が高まる情報を記載していく必要があります。
本記事では、「仕事内容」を魅力的に伝えるための4つのポイントと、それらを巧みに取り入れた3社の実例を合わせてご紹介します。
目次
「仕事内容」を魅力的にする4つのポイント
「仕事内容」は、候補者が応募の意思を固める上で重要な項目の一つです。ここで候補者の心を掴むためには、単なる業務の羅列ではない、解像度の高い情報提供が鍵となります。特に意識すべき4つのポイントをご紹介します!
(1)仕事の概要は1〜2行で簡潔に記載する
仕事内容の冒頭では、「〇〇(プロダクト名)のAPI設計・開発をリードしていただきます」のように、誰が読んでも分かる客観的な業務内容を1〜2行で簡潔にまとめ、ポジションの核心を伝えましょう。
求める人物像に当てはまる候補者から「このポジションは自分に関係がある」と思ってもらうことができなければ、その先の内容を読み進める前に離脱されてしまう恐れもあるからです。
(2)直近の目標・取り組んでほしいことを具体的に記載する
「設計・開発・運用」といった、どの企業でも大きくは変わらない定常業務を並べて書くだけでは、候補者は「自分が働く姿」を明確にイメージできません。
「具体的に、入社後まずは何をするのか」を伝えることが重要です。
例えば、
「現在進行中の〇〇機能の追加プロジェクトに参画し、まずはXX部分の実装からお任せします」
「今後3ヶ月で、パフォーマンス向上のためにXXの改善に取り組んでいただくことを期待しています」
など、短期的な目標や直近で取り組んでほしいことを記載することで、仕事のリアリティが格段に高くなります。
(3)フォーカスしてほしい仕事を記載する
業務範囲が多岐にわたる場合でも、「今、チームとして最も注力していること」や「このポジションの採用者に最も期待すること」を明確に伝えましょう。
「バックエンド開発全般をお任せしますが、特にマイクロサービス化の推進にフォーカスしていただきます」というように、ミッションを絞って提示することで、企業側の期待値と候補者が貢献できることのすり合わせができます。これは、入社後のミスマッチを防ぐ上でも非常に効果的です。
(4) 組織の現状を誠実に伝える
チームや開発組織が「成熟」しているのか、それとも「発展途上で一緒に成長していける環境なのか」は、正直に伝えることも大切です。
例えば、
「開発プロセスはまだ発展途上なため、仕組みづくりから携わってほしい」
「確立された開発基盤の上で、プロダクトの機能開発に集中できる」
というように、現在の自社のフェーズや、開発組織の成熟度がイメージできるよう説明を加えましょう。そうすることで、候補者は自身の志向性(0→1が得意か、1→10が得意かなど)と照らし合わせて、より深くカルチャーフィットを判断できます。
以上が、「仕事内容」を魅力的にするための4つのポイントです。
大切なのは、候補者が「自分が入社したら、こんな仕事にこうやって取り組むんだな」と具体的にイメージできるような情報を提供することです。
魅力的な「仕事内容」3つの実例
それでは、これらのポイントを実践し、候補者の心を掴むことに成功している3社の実例を見ていきましょう。
※編集部注:企業の特定を防ぐため、元の求人票にあった具体的な数値や固有名詞を[ ]で置き換えています。本記事の[ ]内に記載している数値や規模、業界を表す名称等は仮のものです。
A社の求人例
◯仕事内容
【取引実績[400社]以上】国内トップレベルのアプリ設計開発・大規模サービス運用実績多数!スマートデバイス中心のプロダクト成長に寄与したい[モバイル]アプリ開発リードエンジニア
スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを活用したサービスの設計~開発に携わる[モバイル]アプリ開発リードエンジニアを募集します。
当社では、ほぼすべてのプロジェクトが直接契約です。一般的な受託開発とは異なり、CXやUX観点はもちろん、バックエンドのシステムも含めてクライアントと一緒にプロダクトを成長させていきます。お客様の声を直に聞きながら、企画を含めた要件定義、設計、実装、リリース、保守/運用、継続開発まで一貫して携わっていただきます。
当社は、スマートデバイスに特化したアプリケーションの企画・開発・運用実績を強みに、最新アーキテクチャを採用した大規模開発を得意としています。創業からユニークな人事制度を取り入れ続け【成長できる会社】を目指しているため、学び続けられる人と一緒に働きたいと思っています。
◯詳細
【具体的には…】
- プロダクトの設計・開発・リリース後の継続的なサービスディリバリー/DevOps
- 顧客側プロダクトオーナーや社内サービスデザイナー/UIデザイナーとの仕様調整
- 詳細設計の実施、開発標準/ライブラリの選定、コアな部分の実装及びメンバーのコードレビュー
- 開発プロセス(KPT、デイリーミーティング、ブランチ戦略、issue/Pull Requestの運用)の継続的な改善を行いチームをリードする
- 新規技術導入の為の技術調査及び検証
<現在の課題>
- 新卒や中途でもジュニアエンジニアが一定数おり、グループ全体の技術力の底上げを行う育成に課題があります。
- ペアプロやテストを書く習慣の浸透などの施策を行っていますが、育成を効果的に継続的に行う仕組みづくりが課題です。
- また、アプリ開発はUIデザインが実装に及ぼす影響が大きいため、UIデザインチームと連携した上でいかに実装を考慮したデザイン定義を行うかも課題となっています。
【このポジションのやりがい】
- プロダクトの成長はもちろん、チームをリードしながらチームやメンバーの成長に関わる事ができます。
- 顧客やPM・UIデザイナーとの積極的な関わりの中でリーダーシップや関係調整能力を身につける事ができます。
- テックリードによる技術支援があった上で、[モバイル]エンジニアとしての技術力も高める事ができます。
B社の求人例
◯仕事内容
この求人では、実務経験[3年未満]の若いエンジニアを対象としています。
配属グループ・ユニットは先に述べた通り、ご本人様のこれまでのご経験や嗜好性、メンバーとの相性を考慮して決定されます。 入社前の面談・面接の時点で、どのグループ・ユニットにマッチしそうかある程度判断することが多いです。 そのため、面談・面接では私たちからそれぞれのグループ・ユニットについてより詳しくお伝えするほか、これからどんな風に活躍をしていく姿を想像しているか、ご自身の思いをぜひ詳しく聞かせてください。
いずれのグループ・ユニットにおいても、まずは既存メンバーへのキャッチアップ、具体的には採用している技術スタックの習得や[特定の業界]のドメイン知識の獲得が必要になります。 始めは先輩からアサインされる調査業務をクリアする、小さな開発をしてみる、一部の設計を考えてみるといったタスクをこなすところからコツコツ取り組みながらレベルアップし、同時にチームの仲間との人間関係を構築していきましょう。
尚、まだ若い皆さんには、技術領域としてはインフラ([クラウドサービス])からバックエンド・フロントエンドまで基本的にフルスタックで挑戦していただきたいと考えています。 まずは数年にわたり経験を積んでシステム開発の全体感を掴み、その後も引き続きフルスタックで活躍するか、特定の技術領域について深めていくかを選ぶ、そのようなキャリアを会社として推奨しています。 これまでにフルスタックの経験がなくても大丈夫で、幅広く技術を学び力をつけていきたいという意気込みがあれば十分です。
◯詳細
[1] 全グループ・ユニットで共通する業務範囲
アプリケーションの設計・実装、デプロイ、単体テスト・結合テスト作成、CICDの構築を行います。インフラの設計・構築についてもフェーズによっては携わることができます。 最初は先輩エンジニアからアサインされる小さな機能開発、簡易な調査、部分的な設計のチケットに取り組んでいくことになるでしょう。 数か月から半年ほど経過すれば、関与しているシステムの全体像やポイントが掴めてくるはずです。
[2] コミュニケーションの機会
毎日グループまたはユニットで行う朝会・夕会で、個々の業務の確認を行います。 重要なフェーズではプロジェクト朝会を別途行い、不明事項の詳細確認を行います。 週に複数回グループまたはユニットで行うコードレビュー会では、自分は直接担当しないプロジェクトのコードについても議論します。 週に1回程度グループまたはユニットで行う振り返り会では、各プロジェクトの進捗確認を行います。
[3] オペレーションエンジニアユニットの業務
このユニットの業務は多岐にわたります。 ユーザ企業からの調査・問い合わせに対しては、その場で回答するだけではなく、重要度・頻度・対応の手間などで評価を下したうえで、根本的な改善まで行います。 例えば、顧客が登録した不正データの自動連絡ツールを開発して問い合わせを減らしたり、調査ツールを作成して手間を大幅に減らすなど、技術の力でSaaS運用のコストを下げていきます。 その他にも、Docker Imageの共通化によるリリース作業時間の短縮、大規模なリファクタリングなどにも取り組んでいます。
[4] ソリューションエンジニアリング・プロダクト開発ユニットの業務
これら2つのユニットの業務は、新機能開発または新規アプリケーション開発の業務が主です。 業務の範囲としては、設計・開発・デプロイ・テストまでを行う点はオペレーションエンジニアリングユニットと同じですが、追加で新機能の見積り(価格決め)も行います。 開発する新機能や新規アプリケーションをSaaSとしてどのように提供すべきか、ビジネスサイドと連携しながら決定し、設計や見積もりを行います。 具体的な開発内容の一例としては、外部連携のための仕様書を読み込み各種サブシステムから楽に接続できるようIFの設計を工夫したり、ユーザ企業の業務フローを考慮してデータベースを構築するなどがあげられ、設計・開発で高度な技術力・クリエイティビティを発揮して活躍することができます。
C社の求人例
◯仕事内容
◆本求人は、自律制御・コンピュータビジョン・LLM・NLPのいずれかの領域で専門性を持つMLエンジニアを対象としています◆
MLエンジニアをご志望の方で、現在公開中の募集ポジションに適合するものが見つからない方のための求人です。書類選考後、ご希望やご経験に応じた適切なポジションを検討するマッチング面談を設定いたします。応募時「応募先へのメッセージ」欄には、ご自身の強みや得意分野、ご希望の業務内容やアプローチなどを自由にご記入ください。
【MLエンジニアポジション例】
- [ポジション番号]_シニアMLエンジニア / Senior Machine Learning Engineer(自律制御モデル開発) https://●●●●
- [ポジション番号]_シニアMLエンジニア / Senior Machine Learning Engineer(自律制御VLAモデル開発) https://●●●●
- [ポジション番号]_シニアMLエンジニア / Senior Machine Learning Engineer(基盤AI) https://●●●●
※シニアに限らず、プリンシパルクラスの採用も行っています。
当社では、センサーから得られる情報を入力にシステムの制御を行う「AIが全工程を担う自律制御モデル」の開発を行っています。当社のミッションは、完全自動化レベルの自律制御システムの開発を行うことです。現時点では[特定の先進企業]の[特定のシステム]をベンチマークとしており、その性能を上回る自律制御システムをAIベースで開発に取り組んでいます。
モデルの開発には Data-Centric AI と呼ばれるアプローチを取っていますが、実際に学習に用いるデータの裏側には膨大なデータが存在します。膨大なデータからモデル構築を行う機械学習エンジニアを募集しています。
【業務内容】
- 論文や既存実装の調査・再現・実装
- 自社データセットを利用した既存実装の評価
- 実機でのモデル評価・実験管理
- End-to-End の自律制御モデルの実装
- データセットの作成・改善
- オートラベリングの実装
【モデル開発のアプローチは?】
データセントリックなアプローチとモデルセントリックなアプローチの2種類で開発を進めています。この分野のEnd-to-Endモデルはまだ正解はありません。あなたが開発したモデルが次世代の自律制御のスタンダードとなる可能性があります。答えのないフィールドでさまざまなアプローチを試していってください。
【自分のつくったモデルを実機で試して改善していく】
「データセットやモデルを作る→実証実験→実験ログ解析→モデルの管理」という流れで自律制御AIを進化させていきます。自身のつくったモデルを五感で捉えながら改善サイクルを回していきます。机上だけでなく、現実世界からのフィードバックを開発に活かしてください。
◯詳細
◆技術スタック
- 言語:Python
- ライブラリ:PyTorch、OpenCV、MMDetection、ONNX
- ミドルウェア:[ジョブスケジューラ]
- Cloud:AWS、GCP
- プラットフォーム:[エッジデバイス]、Linux
「入社後の働く自分」をイメージできるか
求人票の「仕事内容」は、単なる業務の羅列にするのではなく、候補者が「自身が活躍する姿をリアルに想像できる」よう、解像度の高い情報を提供することが候補者の心を掴む鍵となります。
今回ご紹介した実例では、その点を様々なアプローチで効果的に取り入れていました。
- 直面している「課題」を正直に伝えることで期待する役割を明確にする
- 入社後のステップを具体的に示すことで働くイメージを鮮明にする
- 取り組むミッションの壮大さを語ることで候補者の挑戦意欲を掻き立てる
といった方法を巧みに組み合わせながら、候補者の視点に立った情報提供が実践されています。
ぜひ本記事で紹介したポイントと実例を参考に、自社の「仕事内容」が候補者の働く意欲を掻き立てるものになっているか、見直してみてください。それが、入社後のミスマッチを防ぎ、理想の候補者と出会うための確かな一歩となるはずです。