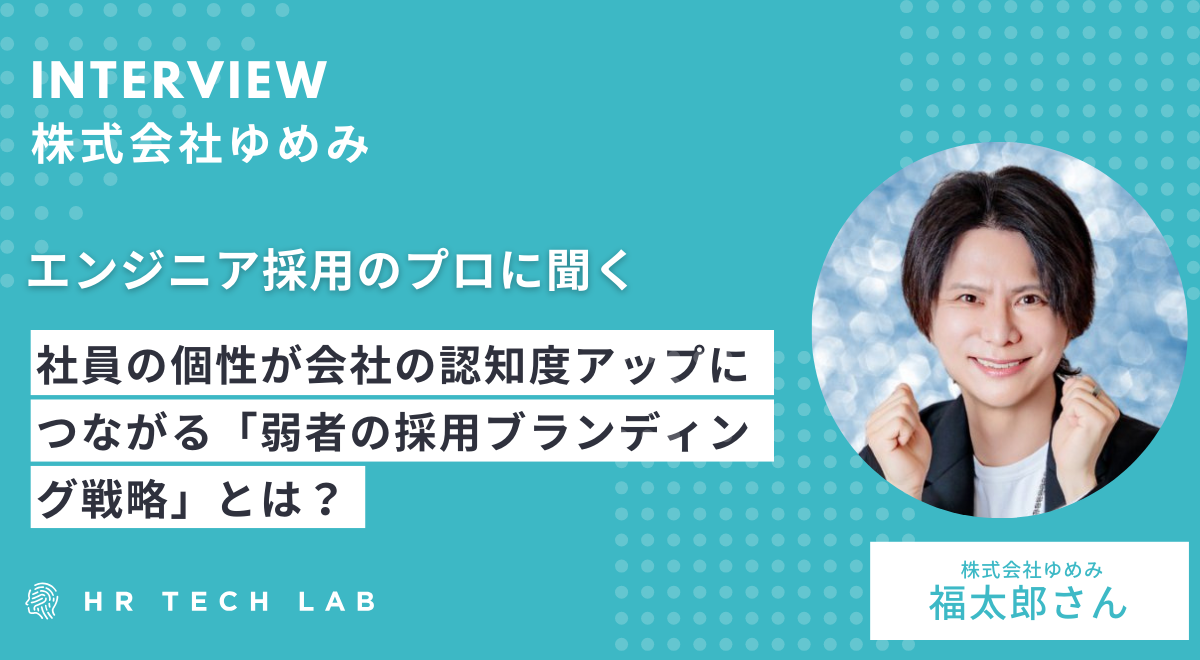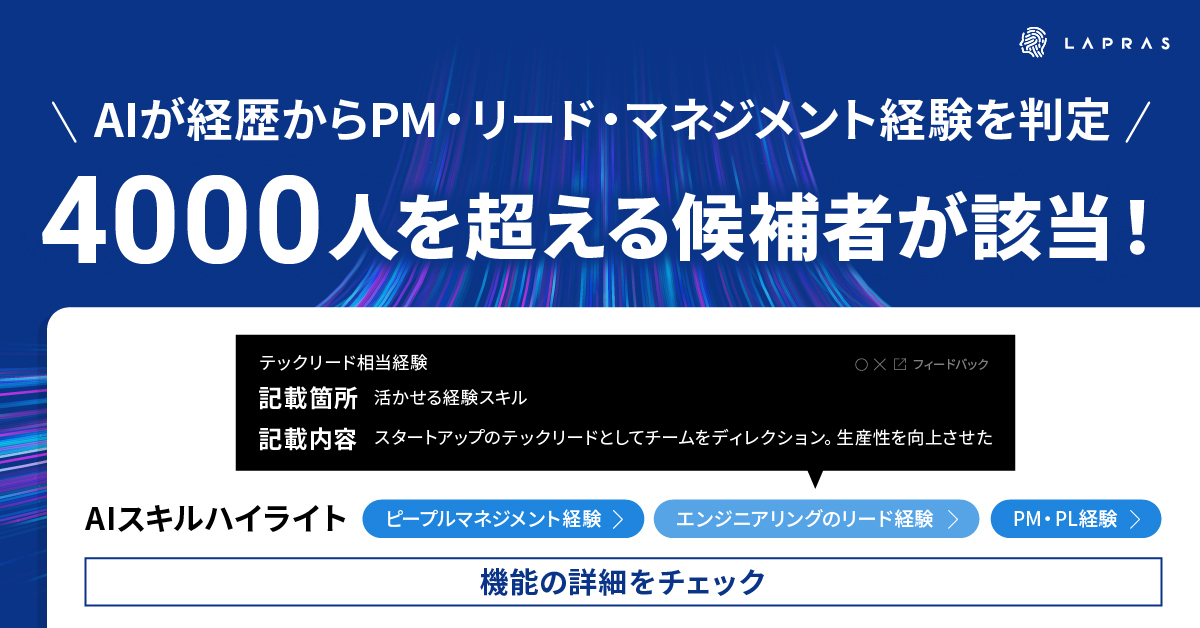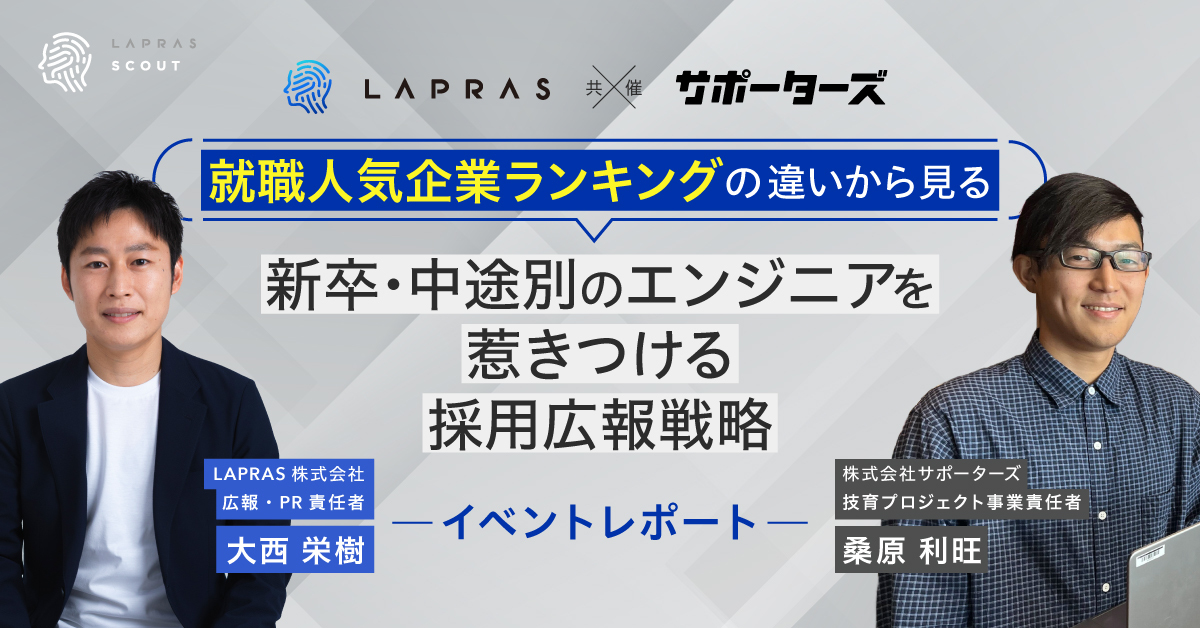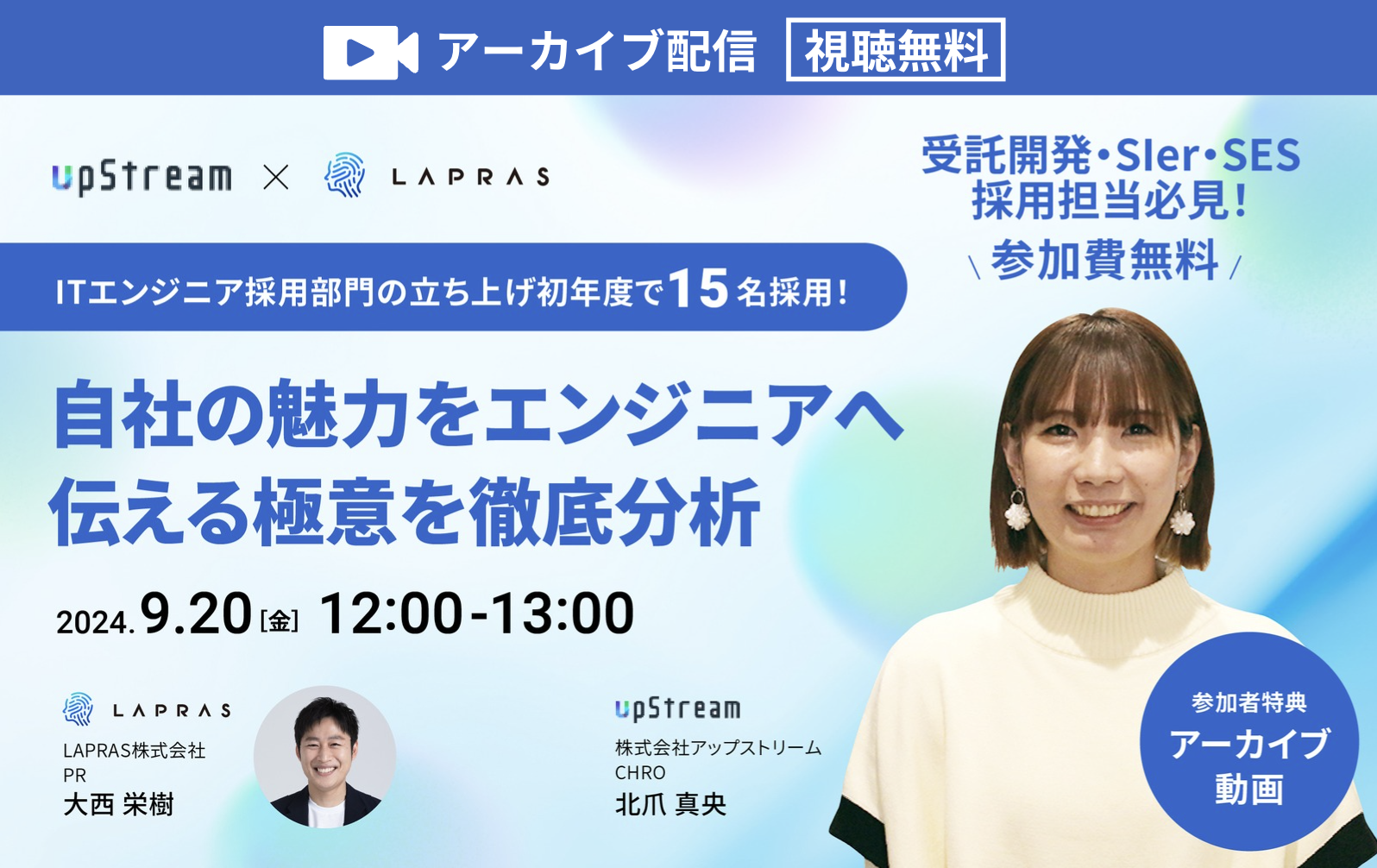「どうしたら自社の強みや特徴をエンジニアの方々に広く知ってもらえるのか?」
エンジニア採用に取り組むにあたって、多くの採用担当の方が頭を悩ませるポイントではないでしょうか。
レバテックの調査(https://levtech.co.jp/research/404011/)によると、IT人材を採用する企業担当者の多くが「エンジニア採用における課題」として、他社との差別化(同調査で1位:36.8%)と、自社の認知向上(同じく2位:36.0%)を挙げています。
こうした課題の解決策となるのが「採用ブランディング」です。そこで今回は、エンジニアからの就職人気企業ランキングで上位常連となっている「株式会社ゆめみ」で採用広報を担当する福太郎さん(福ちゃん)に、スタートアップやベンチャーなど、認知度に課題がある企業でもできる「弱者の採用ブランディング戦略」についてお話をお聞きしました!
《インタビュイー紹介》
福太郎さん/株式会社ゆめみ/執行役員CCO(Chief Communication Officer)
2021年8月よりコーポレート広報・採用広報を担当。ゆめみ入社以前はPR会社2社で約10年にわたりPRコンサルタントとして活躍し、日本パブリックリレーションズ協会認定PRプランナー資格を保有。日本人初のメンズ美容家としても活動し、TVやメディア出演も多数。福岡生まれ神戸育ち、東京在住。愛称は「福ちゃん」。
《株式会社ゆめみ》
デジタルサービスの「内製化」支援を中心に、大手企業からスタートアップまで幅広いクライアントと共にWebサービスや公式アプリの企画・開発・運用を手がけているDX内製化支援のリーディングカンパニー。全世界で延べ600社&6,000万MAUが利用するサービス開発に携わるほか、エンジニアの成長環境を重視したユニークな人事制度やカルチャーでも注目を集めている。
・株式会社サポーターズ「2026年卒対象 ITエンジニア就活人気企業ランキング」(ハイクラス学生編)9位
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000045025.html
・一般社団法人日本CTO協会「開発者体験が良いイメージのある企業ランキング2024」4位
https://www.yumemi.co.jp/dxd2024
職務経歴に隠れたスキルを見つけませんか?
LAPRASの新機能「AIスキルハイライト」でリード・PM・マネジメント経験を持ってる候補者を候補者を簡単に見つけることができます!
AIスキルハイライトの詳細はこちら目次
スタートアップでも大手と戦える「弱者の採用ブランディング戦略」とは?
Q1.ゆめみさんが「採用ブランディング」に注力することになった背景・きっかけを教えてください。
福太郎さん:一番大きかったのは、新卒採用の激化ですね。特に大企業・メガベンチャーとの人材獲得競争の中に巻き込まれていく中で「優秀なエンジニア人材」の採用ニーズが劇的に高まっていきました。まず、ゆめみのことを知ってもらわないと就職先の選択肢にも入れてもらえないので「他社に埋もれてしまわないように、どう差別化していくか」「いかにゆめみを知ってもらい、選んでもらえるか?」を考えていかなければいけませんでした。
Q2.採用ブランディングにどんな戦略を掲げていますか?
福太郎さん:一言でいうと「弱者の戦略」です。「孫氏」みたいな話になりますが「可能な限り戦いを避けつつ、いかに出し抜くか」が最初のポイントです。とはいえ、どうしても戦わなければならない局面は訪れるので、そういうときは「大手ができない・やりたくないことをやる」というスタンスで戦おう、と考えました。
具体的には「メンバーの個を前面に打ち出すアウトプット」で差別化を図っています。メンバーの個を前面に出そうとすると、発信するトンマナやメッセージ性のコントロールが難しくなっていきます。なので、一般的な企業の場合だと「だったら最初から発信しないでおこう」となってしまいがちです。ゆめみはそこを逆張りする形で、まずメンバーの際立ったキャラクター・個性を知ってもらい、そこからゆめみという会社を知ってもらうという順序で認知獲得を設計しています。
同時に、他社の一歩先、二歩先でもなく「半歩先」を狙った絶妙なタイミングで施策を打ち続けることも重視しています。そのときは、一点突破でリソースを集中投下して、圧倒的なポジションを築き、ライバルの戦う意欲を挫く、という戦略を取っています。
– 大企業やメガベンチャーではリスクを意識して避けるであろう、メンバーの「個」を打ち出す戦略を取ったのですね。
福太郎さん:はい、リスクを背負った分だけ認知をとれるチャンスも広がります。短期間で認知が高まるとアンチや抵抗勢力が生まれる可能性もありますが、それを補って余りあるメリットを生み出せます。
そして、時間の経過とともに実態への理解が深まってくると「あれ?ゆめみって意外とちゃんとしてる?」というギャップからポジティブなイメージへと転換する、というのがゆめみの戦略ですね。
個人のアウトプットを評価・称賛する組織へ
Q4.具体的にどんなことに取り組んだのでしょうか?
福太郎さん:大きく3つの狙いがあるので、順番に説明します。
大きな市場を選ぶ
福太郎さん:1つ目は「大きな市場を選ぶ」ことです。ITエンジニアの方々は概ね、働く環境の衛生要因よりも、自己の成長を重視する傾向があります。なので、ゆめみとしては「成長環境No.1」を目指すことにしました。単にメッセージを掲げるだけでなく、実際にエンジニアが思う存分腕を磨ける、成長できる環境を整え、それをしっかり発信していくことにして「体制づくり」と「メッセージの打ち出し」を両輪に足場を組みました。
戦いが少ない空白地帯を狙う
2つ目は「戦いが少ない空白地帯を狙う」ことです。「技術アウトプット力」を最大化することで、ゆめみの技術力や「エンジニアの成長環境がある」ということが示せると考えました。
2017年までのゆめみは、恥ずかしながらアウトプットする文化がありませんでした。積極的にアウトプットされる人が称賛されることもなく、当時テック界隈で主流だったオウンドメディアにも取り組んでいましたが、レビューでの赤入れも多かったりと、書き手のモチベーションが上がりづらい状況でした。結果、記事の本数も増えない、PVも伸びないというネガティブスパイラルに陥っていました。記事の名義も匿名だったので、書くことにインセンティブも生まれない状態だったんです。
ターニングポイントになったのは2018年。この状況を転換するために、全社を上げて「アウトプットをすることは偉い」という方針を打ち出しました。
具体的には、オウンドメディアはクローズし、当時ブレークの兆しを見せていたQiitaやnoteといった外部のプラットフォームに、個人名義でアウトプットする方法に切り替えました。
そこで発信した内容は、書き手のポータブルアセットとして「キャリアアップの際の武器になります」という点を繰り返し発信し、アウトプットのための時間も、業務時間としてカウントするようにしました。
さらに、心理的な動機付けとして「書く意欲」が高まる仕組みづくりをしました。社内Slackに「アウトプットの報告チャンネル」を作り、そこでアウトプットの報告をするとメンバーからスタンプがたくさんつく、「この記事良かったよ!」というコメントとともに、社内にシェアされる場を設けました。
また、ゼロイチから一気にドライブさせるために、期間限定で金銭的なインセンティブも用意しました。中途半端な形ではあまり効果はないのでリモートワーク推進キャンペーンと紐づけて「2年間・3ヶ月に1回・賞金100万円を一人がもらえる」という社内キャンペーンを打ち出しました。
これらの取り組みで「アウトプットする人は社内的に評価・称賛される」「報酬という形でも貢献が反映される」という社内文化を定着させていくことができました。
アウトプットに積極的な人が集まる好循環を生み出す
ー「どうやってアウトプット文化を社内に定着させるか?」という点を重視されていたんですね。
福太郎さん:社員全員に「書いてください」「お願いします」と言っても、うまくいかないということは過去の経験からわかっていたので、まずはトップランナーに全力疾走してもらう仕組みづくりを実践したら、結果的にうまくいきました。ここに至るまでに、いろいろな試行錯誤の連続があってこの方法に行き着いた、という感じですね。
戦う意欲を挫く数的優位
そして、3つ目のポイントである「戦う意欲を挫く数的優位」を築いていきます。「アウトプット文化」が社内に根付いた結果、ゆめみがQiitaの上位ランカー常連になることができました。そうしてテック界隈で局所的な認知度が高くなると、
「ゆめみさんのお名前、よくQiitaで見ます」
「無職やめ太郎さんやmpywさんって、Qiitaでよく見ますけど、ゆめみの方だったんですね」
という声をかけてもらえるようになりました。「組織としてアウトプットする文化が根付く」「個人としてスタープレイヤーが生まれる」という状態ができると、対外的に「ゆめみ=技術アウトプット強い会社」というイメージを持ってもらうことにつながります。結果として「技術アウトプットに積極的なゆめみで、ぜひ働きたい」という人が集まり、さらにアウトプット文化が強まる、というスパイラルが生まれていきました。
ーアウトプット文化が定着し、Qiitaで1位を取るなどの実績を挙げた結果、「アウトプットに積極的な人が集まる」という形で採用成果に返ってきたということですね。
福太郎さん:実は、今でも社員全員がアウトプットに積極的な人ばかり、というわけではないんです。しかしながら、新卒・中途で入ってくる新しいメンバーの中には「有名になるぞ!」という前のめりな意欲を持っている人がたくさんいます。そういうメンバーが入ってくることで、社内の空気も変わってくるし、触発されて「久しぶりにアウトプットしてみようかな」という気持ちになる既存のメンバーもいます。すでにテック界隈で有名になっている同僚に影響される形で、他の社員もアウトプットに積極的になるなど、社内的にも好循環が生み出されていますね。
まず旗を立て、短期間で大きな変化を起こす
Q5.「アウトプット文化」を根付かせる取り組みの中で、印象に残っているものはありますか?
福太郎さん:「旗を立てる」ことがすべての出発点になりましたね。2018年の「アジャイル組織宣言」、2019年「リモートワーク先端企業宣言」のように「ゆめみは変わります!」という旗を立てて、堂々と宣言して動き出しました。
そして「動き出したら短期間で一気に変える」という点を意識していました。この方法だと一瞬混乱は起きますが、先に変化に対応できたメンバーから順番に橋の向こう側に渡っていけるので、着実に変化していけると考えていました。
特に影響が大きかったのは、画像でハイライトしている部分ですね。先に述べた「Qiitaなど外部メディアでの個人発信」以外だと、月100時間おこなっていた社内勉強会を、他社とコラボする「社外勉強会」に切り替えました。社内では「コバンザメガベンチャー作戦」と冗談交じりに言っていたんですが、とにかく「メガベンチャーとコラボする」という点を意識していました。ゆめみのロゴが、認知度の高い素敵な企業のロゴと並ぶという状態を作れるよう、戦略的に取り組みました。
さらに「タレントプロデュース」ということで「社内のタレント」を発掘し、打ち出していきました。「X大喜利」では、エンジニアの方々が好むような「エンジニア業界あるある」をゆめみの公式Xアカウントで発信し続けていき「社を上げて、真剣にふざける」という方針で、テック界隈での視聴率を取っていこうとしていました。
ゆめみの場合は「真面目で、技術力の強いエンジニアが集まっているのに、発信がうまくできていない」という実態があったので「発信さえうまくできれば、その実態を知ってもらえるのではないか」という考えで戦略を組み立てていきました。
認知、認識を経て自社のファンを作る
福太郎さん:PRの世界では以下のような「認知」と「認識」という言葉があります。
認知:知ってもらえている
認識:実態を理解してもらっている
ゆめみの場合は「まず認知してもらって、そのあと認識してもらうことでファンになってもらおう」という狙いから、こうした経緯を辿ってきました。「認知・認識」でスタートアップが大手・メガベンチャーに対抗するには「なにかで思い切り振り切る」ということが必要なのではないかと思います。
人を傷つけず、メンバーの個性が活かせる戦略
Q6.社外に向けて、自社の魅力を発信していくときに重視していることはありますか?
福太郎さん:キーワードは「ユニークネス・遊び心・おふざけ」です。ゆめみでは「自慢は✕、自虐は◯」と言っているのですが、とにかく鼻につくと嫌われるので「自慢したり、マウントをとりにいったりは絶対にしない」「反論をしない」ことが大事です。「笑いをベースにした自虐によって、共感と応援を引き出す」ことが基本的な姿勢ですね。
Q7.実際に発信役を担う、社内メンバーの個性もカギを握りそうです。ここを魅力的に発信していくにはどんな工夫が必要ですか?
福太郎さん:たとえば「無職やめ太郎(https://x.com/Yametaro1983)」は、Qiita上位ランカーですが、Xではユーモア交じりの自虐的なキャラクターが受けて応援されています。「そば屋(https://x.com/sobaya15)」はそれとは対象的に、イベントなどでも年中この格好で、なにかにつけて「仕事休みます」「ビール飲みます」という発信をしているキャラクターです。
それぞれのメンバーが元々持っている個性を活かしつつ「自慢ではなく自虐で共感・応援を引き出す」というゆめみのスタイルを守っていこう、とゆるやかな形で取り組んでいます。SNSでの発信も特に制限は設けていません。1点だけ「人を傷つけないようにしよう」というシンプルな約束事だけを徹底しています。
企業の評価・好感度を高める「パーセプションギャップ」の設計
Q8.メンバーの個性が伝わるユニークなやり方ですね!遊び心やおふざけを重視しているのには理由があるのでしょうか?
福太郎さん:上記の画像にある「第一認識」から「第二認識」に至る流れの中で「パーセプションギャップをあえて作る」という狙いがあるからです。
第一認識の部分は、先程挙げた「ユニークネス・遊び心・おふざけ」に則った発信を、全社的に盛り上げています。この段階では「笑い・謙遜・自虐」を基本姿勢にしていますが、大企業やメガベンチャーでは、ここまで振り切った発信は難しいはずなので、確信犯的にやっています。
こうした発信をしていると「自由度が高そう・楽しそう・親しみやすい」とポジティブに受け止めてくれる人も多く出てきます。ただ一方で「浅はか・何やっているかよくわからない・技術力高くなさそう」といった、ネガティブなイメージを持ってしまう人も一定数出てきます。そうした副作用を織り込んだうえで「強烈な印象を与える認知獲得」を重視しています。
なぜかというと、時間の経過とともに「第二認識」の段階で新たなタッチポイントに触れてもらう機会があると「あれ?ゆめみって第一印象はあまり良くなかったけど、でも実は…」というパーセプションチェンジが発生します。
《でも実は…》
・プロダクト設計やブランディング設計がよく考えられている
・実績が強い(本業やQiitaのランキングなど)
・メンバー個々人の技術力が高い
このように、実態を知ることによって「パーセプションギャップ」が生まれ「実態以上に評価される」という状況を生み出せます。このギャップが大きければ大きいほどブランドプリファレンスを高めることができるので、それを狙って戦略的におこなっています。
「弱者の採用ブランディング」に取り組む際のポイント
Q9.「弱者の採用ブランディング戦略」は、大企業やメガベンチャーでなくても実践できるとのことでしたが、これから採用ブランディングに取り組む企業は、最初にどんな手順で進めたらいいでしょうか?
①自社の強みやクセを見出す
福太郎さん:ポイントは5つあります。1つ目は「自社の強みやクセを見出す」ことです。具体的には「やたら◯◯な社員が多い」「よく◯◯をイジられる」といった、自社のクセを見出すのが大事です。
たとえば「社員にめちゃくちゃパリピが多い」「体育会系が多い」「保守的で真面目」とか、企業ごとになにかしらの「社風」があるはずです。そこを言語化してみるのが第一歩ですね。
②社内の奇特層(タレント)を発掘する
福太郎さん:2つ目のポイントは「社内の奇特層(タレント)を発掘する」ことです。どんな組織でも程度の差はあれ異才を持つ人はいるはずです。「クセが強い人・個性的な人」「変わった趣味を持っている人」といった社内タレントを何人か見つけていきましょう。
ゆめみの場合は組織設計として「全社員の2.5%」をタレントとして位置づけています。社員全員が(向いていない方も含めて)タレントのような振る舞いをしなければいけない、というわけではないので、ご安心ください。
また、奇抜なことをするのが目的でもなければ、唯一の手段というわけでもありません。社内の奇特層が「元々持っている個性を活かす前提で、際立たせるプロデュースをする」という考えで良いと思います。
③意図的なパーセプションギャップの設計
福太郎さん:3つ目は「意図的なパーセプションギャップの設計」です。ゆめみという「組織」の例を挙げてご紹介したような「でも実は…」という意外性を生み出す設計は、組織の場合でも、個人の場合でも重要です。
たとえば「普段は真面目な人が、たまにふざけた発信をする」、逆に「いつもふざけている人が、たまに真面目なことを言う」といったことをすると、意外性が生まれます。私の場合は、普段はXでふざけた投稿をしているので、10のうち1は真面目なことを投稿するようにしています。硬軟織り交ぜながら、意外性の振り幅を大きくしていくのがいいと思います。
④適切なインセンティブ設計
福太郎さん:4つ目は「適切なインセンティブ設計」です。心理的インセンティブと金銭的インセンティブの両軸で設計できるといいでしょう。なにもない状態で「とにかく発信するんだ!」「個性的に振る舞え!」と言われて、なんの見返りもなかったらモチベーションも生まれないので、やる気を引き出す仕掛けづくりを行います。禁断症状を生むので、金銭的インセンティブについては最初から期間限定で打ち出すことをおすすめします。
⑤経営層の巻き込み
福太郎さん:最後の5つ目は「経営層の巻き込み」です。個人的には、これが一番大事だと思っています。「ここまでならやっても大丈夫」というラインを担保して、心理的安全性を確保することで、社員も全力でユーモアを開放できるようになります。
経営層を巻き込んで「こういう企業を目指す」という旗を立て、率先してうまく実践できた人をみんなの前で褒めるなど「うまくできている人に反応する・称賛する」という姿勢を示すこと、メンバーが全力で踊れるような舞台を整えることが大事だと思います。
欲を言えば、ゆめみがそうであるように「代表など、経営層が自ら手本を見せる」ことができるとなお良いですね。思わず「そんなにふざけて大丈夫?」と社員が心配してしまうくらいやり切れると、他のメンバーも安心して後をついて行けます。ゆめみの場合は、ちょっとやりすぎかもしれませんが(笑)
個人のブランディングの後押しが、組織の評価に返ってくる
Q8.本日はありがとうございました!最後に読者の方に向けてメッセージをお願いします!
福ちゃん:「個人のブランディングを組織が後押しする」という構図が増えていくと、幸せな組織や個人が増えていく、と思っています。個人の権威性・レピュテーションが高まると、それは結果的に組織ブランドにも還元されていくはずです。
個人はシンプルに人材としての市場価値が高まりますし、所属している組織も「あんなすごい人がいる会社だ」という評価が得られます。
・個人は自身のブランディングを高めることで組織に還元する
・組織は個人のブランディングを支援することで、結果的に自組織の評価を高める
こうした循環の輪をいろいろな個人・組織で増やしていければ、それはやがて様々な業界で全体的にプラスになっていくはずです。なので、特定の企業や個人がノウハウを隠すのではなく、オープンにシェアリングしながら経済圏を活性化させていくと、個人にとっても、組織にとっても幸せな世の中になっていくと思います。
私たちみんなで、そんな世の中にしていきましょう!
ー本日はありがとうございました!